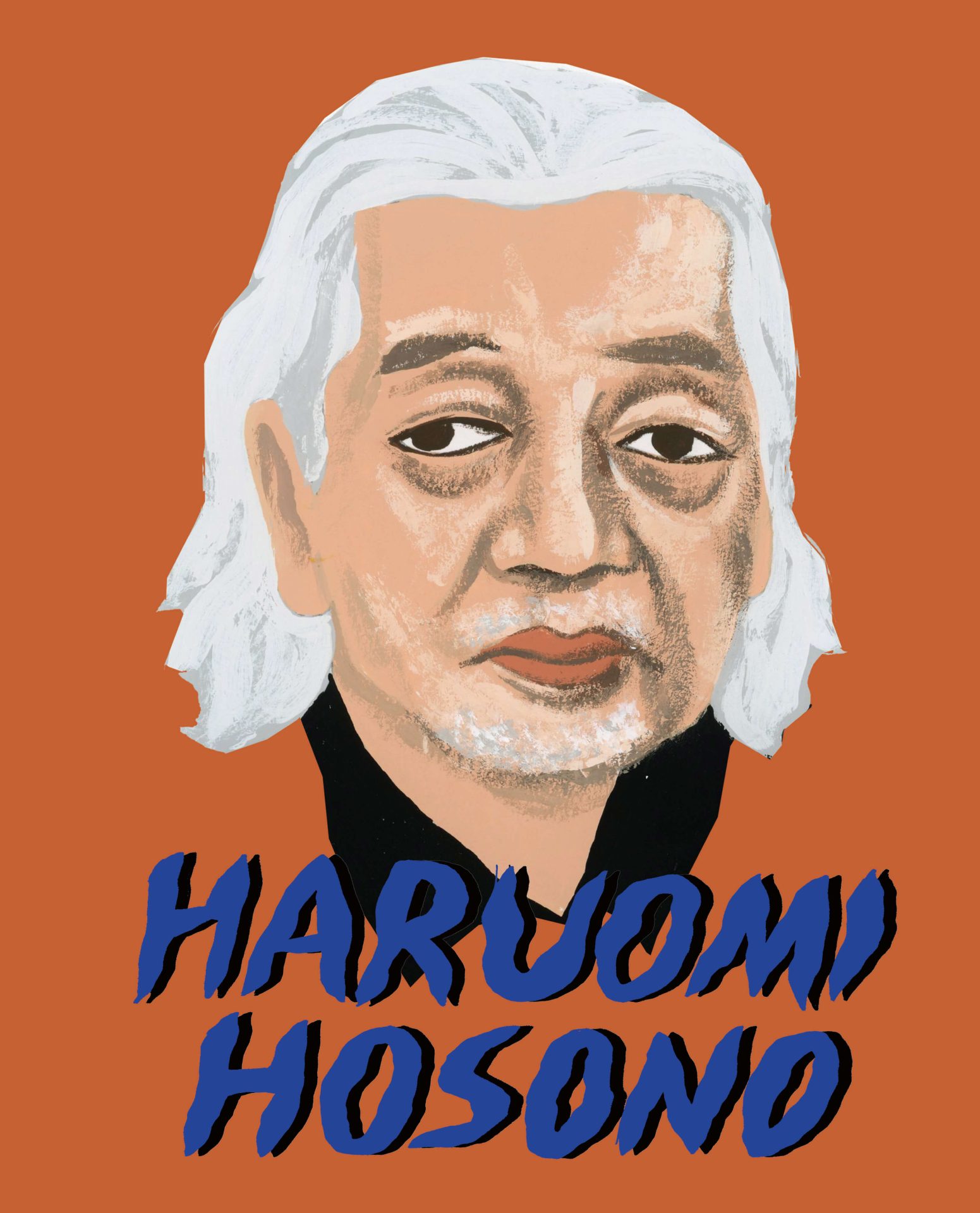【LIFE MUSIC. ~音は世につれ~】第78回 場所と時間、そして自身の記憶を旅する人 by 青野賢一
ESSAY / COLUMN
〈NO MUSIC, NO LIFE.〉をテーマに音楽のある日常の一コマのドキュメンタリーを毎回さまざまな書き手に綴ってもらう連載〈LIFE MUSIC. ~音は世につれ~〉。今回のライターは青野賢一さんです。
『トロピカル・ダンディー』が今年で発売から50年ということで、先ごろ記念盤もリリースされた細野晴臣。北米から「カリブの島々とそれを囲む海、そして、向こうにかすむ大陸と港」(細野晴臣によるライナーノーツ「島について」)へと関心が広がるなかでできあがった同作は、狭山の米軍ハウスというアメリカのミニアチュールを出て、本格的な音楽的航海へと出発した作品ととらえることができるだろう。
先に引いたライナーノーツには「色々な要素が混じり合ったごった煮の音楽が、その国の人、あるいは土地柄とミックスして出て来る音楽こそ、本当に面白い音楽だと信じている」ともあり、それらに最後のひと味として醤油をたらすようなことをやってみたくなったと書かれている。「“ソイ・ソース” ミュージック」と氏が名づけたこの音楽は、実はその音楽がどんな経緯でそこにたどりついたのか、つまりどこからやってきてどういった道筋を経てきたかを知ることが不可欠であるように思う。音楽をときほぐし、ていねいに腑分けをして来歴を明らかにする––––この作業はその音楽の歴史をさかのぼる旅でもあるわけだ。
音楽とは人間の営みによって生まれるもの。とすれば、その道筋をたどる行為はそのまま人や土地の歴史を探究することに重なってくる。いわば民俗学のようなものだ。そのうえで氏は1978年のイエロー・マジック・オーケストラ(YMO)のファースト・アルバムで「東京民族」の音としてふたつの「コンピューター・ゲーム」を取り上げている(ちなみに坂本龍一は同年リリースの『千のナイフ』で「Das Neue Japanische Elektronische Volkslied」、日本語にすれば「新しい日本の電子的民謡」という曲を発表している)。「トロピカル三部作」と称される『トロピカル・ダンディー』、『泰安洋行』(1976)、『はらいそ』(1978)に続いて世に出たYMOのファーストは、表面上はそれまでとは異なるアプローチで古くからの細野ファンを戸惑わせたが、アルバムA面は「トロピカル三部作」と地続きといっていいだろう。先に記した「コンピューター・ゲーム」、そしてマーティン・デニー「Firecracker」のカバー、アラブ風味の「Simoon」、ファンキー・サーフ・ミュージック「Cosmic Surfin’」という具合に、電子的民俗的ごった煮音楽で細野ワールド全開なのだ(一方、B面は坂本龍一、高橋幸宏を前面に出した内容で、それ以降のYMOの方向性を示唆しているようである)。
YMOの活動期間中は、氏の音楽の来歴をたどる旅は表立ってはいなかったが、散開後はふたたび顕著になってゆく。1980年代半ばには日本各地の霊地を巡り「観光音楽」を掲げた作品を発表。やがてワールド・ミュージックにも関心を寄せて1989年にはアルバム『オムニ・サイト・シーイング』をリリースしている。国内であれ海外であれ、信仰や文化の端緒となった事象に光をあてて観る=観光することから音楽を紡ぐ––––作品のジャンルやテイストだけに着目するとわかりにくいかもしれないが、氏のアプローチにはこのように一貫したものがあるように思う。
音楽とそれを育んだ人や土地の時間をさかのぼる旅は、21世紀に入ると自身の内面、記憶も対象になった。自分を通り抜けていった音楽のうち、長い時間を経てもなお心にとどまっているもの。それらを改めて表現した『Heavenly Music』(2013)や『Vu Jà Dé』(2017)は近年の氏を代表する作品といえるだろう。
こうして氏のことを考えるとき、わたしの頭にはいつもローマ神話のメルクリウス(ギリシャ神話ではヘルメス)が浮かんでくる。メルクリウスは金属でありながら液体でもある水銀に象徴される、異なるものや対立するものを結合させる存在。一見、直接的な関連がなさそうな事象を、それぞれの来歴までさかのぼり想像力を働かせ結びつけて表す氏のアウトプットは、さながら音楽の錬金術といったところであり、それゆえいにしえの錬金術の根本的象徴たるメルクリウスの名がいつも想起されるのだ。そんな推量だが、『マーキュリック・ダンス ~躍動の踊り』(1985)というアルバムがあることを思えば、あながち間違いでもなさそうではないか。ちなみにメルクリウスは旅人の神でもある。